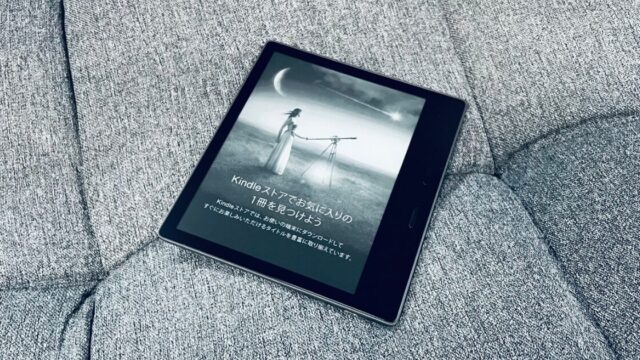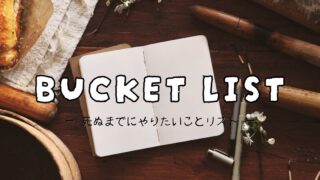「にわか本好き」の浅田めめんとです。
いや、読書好きを名乗るのに条件なんてないんだけど、なんとなく「本の虫」とか「活字中毒」と呼べるようなガチ勢の方を目にしていると、「私は読書好きです!」って言いにくいんですよね。
読む本だいぶかたよってるし。
これはどの趣味にも言えることなんですが、大体のことは「にわかなんですけど~」と予防線を張って生きている気がします。
たぶん自意識過剰でしかない。
最近、文芸評論家の三宅香帆さんを知り、著書を読んだり、出演しているYouTube動画を見るようになりました。
三宅さんの著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、中央公論新社が主催する「新書大賞2025」にも選ばれ、ベストセラーとなっています。
…なんてエラそうに語っていますが、この「新書大賞」という賞の存在も、三宅さんのYouTubeで知りました(笑)
というか、今まで本を買うときに「新書」という存在をあまり意識したことがありませんでした。
単行本か文庫かは、「このハードカバーの立派な装丁が素敵!」とか、「読んでみたかった本が文庫化してる!お値段的にもサイズ的にもありがてぇ!」とか、いろいろ感じることはあります。
でも、「新書のコーナーに行ってみよう」とか、「新書で面白そうな本ないかぁ」とか、全然考えたことなかったかも。
なんなら文庫とのちがいもあまり理解していなくて、過去にたまたま購入した新書に対しても、「なんかこの文庫本、細長いし表紙がどれも似てるな」程度にしか思っていなかった気がします。
そんな新書ですが、意外と興味深い世界だぞ!と、「にわか本好き」なりにだんだん分かってきました。
そもそも「新書」とはどんな本なのか
そもそも新書って何?文庫本とどうちがうの?
ということで、疑問が湧いたときはとりあえずGoogleGeminiさんに聞いてみます。
要約するとこんな感じ。
新書とは、比較的手軽に読めるように作られた、一定の形式で刊行される書籍のシリーズのこと。
政治、経済、社会、歴史、科学など、幅広い分野のテーマを扱っています。
専門的な内容を一般読者向けにわかりやすく解説したものが多く、教養や知識を得るための入門書として適しています。
その他の特徴としては、
- 標準的な寸法は173mm×106mm(縦長でスリム)
- 比較的手頃な価格設定
- ソフトカバー(並製)で、持ち運びしやすい
といったことが挙げられます。
また、出版社ごとに表紙などの装丁が統一されているのも特徴的。
書店の棚って基本カラフルでカオスですが、新書コーナーは独特の整ってる感が漂っていて、居るだけで知的になった気分になれます(アホの発想)。
今まで新書になじみがなかった理由のひとつに、統一された表紙で中身のイメージが湧きづらい…というのもあったんですが(笑)
先述のとおり、内容としてはかなり幅広いテーマを扱っています。
個人的には「文体が堅くてハードルが高い専門書」みたいなイメージが強かったのですが、どちらかというと「専門分野の入門書」としての役割を意識してつくられているようです。
他にも実用書や時事ネタ、ルポなど、ノンフィクションを広く扱っていると言えます。
そうは言っても、やはり読み慣れていない方にはとっつきにくい本もあるかもしれません。
ただ、当然ながら著者やジャンル(あとは出版社ごとの雰囲気?)によっても読みやすさはだいぶ変わるので、「新書」というだけでなんとなく避けてしまうのはもったいない!
…と、私自身も最近気付くことができました(笑)
三宅さんが「新書って面白いよ!」とたくさんアピールしてくれたおかげです!
文庫本とはどうちがうの?
新書に対するイメージが少し湧いてきたかと思いますが、「サイズや表紙の他に、文庫とのちがいはあるの?」と思う方もいるかもしれません。
いちばんの大きなちがいは、扱うジャンルの幅ではないでしょうか。
新書は特定分野の入門書となるような内容がメインですが、文庫本は、小説やエッセイ、古典など文芸書が多いのが特徴です。
場合によっては、過去に出版された漫画などが文庫化する場合もあります。
同様に、単行本(大きいサイズの本)として出版された本が後から文庫化されるというパターンも多く、単行本にはなかった解説やあとがきが追加されるという楽しみもあったり(有名な作家さんの小説なんかは文庫化されやすいですよね)。
一方、例外はありますが、新書は基本的に書きおろしの作品が多いそうです。
余談ですが、三宅香帆さんの『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書)は、単行本が新書化された珍しいパターンの書籍です。
けっこうあるぞ、新書レーベル!
今まであまり出版社やレーベルを気にしていなかった私ですが、せっかくなので、どんな新書レーベルがあるのか調べてみることに。
Wikipediaに『新書レーベル一覧』というページがあったのでありがてぇ!と覗いてみたところ、思っていたよりたくさんあって驚きです(そして廃刊・休刊の欄の多さにもびっくり。諸行無常……)。
ここでまたGoogleGeminiさんに「代表的な新書レーベルを教えて」とお願いしたところ、こんなリストをつくってくれました。
- 岩波新書(岩波書店)
- 中公新書(中央公論新社)
- 講談社現代新書(講談社)
- 新潮新書(新潮社)
- 文春新書(文藝春秋)
- 幻冬舎新書(幻冬舎)
- 集英社新書(集英社)
- 光文社新書(光文社)
- ちくま新書(筑摩書房)
- NHK出版新書(NHK出版)
新書ビギナーゆえに、「このレーベルはこういう傾向があって…」と語れないのが悔しい。
ただ、新書は小説などとちがい、タイトルだけで「興味があるかどうか」を判断しやすいので、興味を持った本がどのレーベルなのかに注目してみるだけでも、自分の好みの傾向が見えて面白いかもしれません。
ちなみに、私が(記憶があるなかで)初めて買った新書は『物語スペインの歴史: 海洋帝国の黄金時代』(中公新書)だったと思います。
中公新書は歴史系の本のイメージがつよい。
なかなか渋いチョイスだと思われるかもしれませんが、そのときハマってた漫画の影響というオタク丸出しな事情があります。
私が思う「新書」のいいところ
興味が赴くままにまとめていたら、調べたことだけで終わってしまいそう(笑)
せっかくなので、最近新書に興味を持ち始めた私が思う、「新書」のいいところについてお話して終わりたいと思います。
私が「新書っていいかも」、「ここが面白いな」と感じたところは、主につぎの4つです。
- 知らない世界に興味を持つきっかけになる
- あらゆる問題提議に触れられる
- 文章を読む力が鍛えられる(気がする)
- 比較的気軽に読書体験を増やせる
①知らない世界に興味を持つきっかけになる
一番はこれです。読書全般に言えることでもありますが。
やはり「専門分野の入門書」的立ち位置の本や、実世界で起きていることを書いたノンフィクションがメインというだけあって、タイトルだけで「なにそれ知りたい!」「いったいどういう世界なの?」と思わせられます。
最近は書店でたまたま見かけた『珈琲の世界史』という本を買いました(まだ積読です)。
あとは夜の世界や大人向けの産業(マイルドな表現をしています)について真面目に語られる本なんかも、けっこう興味深いです。
珈琲よりもよっぽど知らん世界ですので。
②あらゆる問題提議に触れられる
今までノウハウを語るビジネス書や、文化史、エッセイ、ライフスタイル系の本などを読むことが多かったです。
そのため、「社会ではこんなことが起きているが、これでよいのだろうか?」と直球で問いを投げかけたり、意見を語るうえで特定の対象に批判的な態度を示したりする本にはあまり触れてきませんでした。
そんなの当たり前だろうと思う方もいるでしょうが、私にとってはカルチャーショックに近い衝撃(笑)
もちろん著者の意見・思想を正しいと思うかどうかは読み手次第です。
本のなかで答えが出ているとも限りません。
ただ、知らなかった世界に飛び込んだうえで、「そんなこと考えたこともなかったなぁ」とか、「私はちょっとちがう意見かも」とか、頭のなかで対話してみるのも、ある種の刺激になると思います。
自分の意見を持つの、わりと苦手なタイプなんですけどね…(ぼんやり生きてきたので…)。
自分の頭で考える練習として、これからもいろんな意見に触れてみたいです。
③文章を読む力が鍛えられる(気がする)
普段から読み慣れていないと、新書のように文字がびっしり!という本は、読むのにけっこうなエネルギーがかかります。
物理的に字も小さいしね(笑)
でも、「文字ばかりだから」「自分に読めるか不安だから」と、言わば食わず嫌いのような理由で気になるテーマの本を避けてしまうのは、なんかもったいないのでは?と思うようになりました。
読みやすそうなものからでも何冊か挑戦してみると、「あれ?案外自分もいけるぞ!」と自信がついてくるはず。
そこから次に読む本の選択肢が広がっていき、結果的には文章を読む力自体がついてくるんじゃないかなぁと思っています。
実体験というより、3/4くらいは願望ですが(笑)
④比較的気軽に読書体験を増やせる
新書の多くは1,000円前後。
先述のとおり入門書的なものが多く、そこまで置いてけぼりになることもないと思います(私もビギナーなので一概には言えないけど)。
単行本の文化史や専門書なんかは2,000~3,000円超えも多いですし、バッグに入れて持ち歩くには鈍器すぎる。
その点新書は薄くてサイズも小さいので、場所をとらないという物理的なメリットもあります。
文芸作品が読みたい場合は対象から外れるとは思いますが、意外と挑戦しやすく、読書体験を増やしていけるのが新書の魅力のひとつではないでしょうか。
以前は正直「見た目に個性がなくてさみしい」というイメージがありましたが、だんだんと「このサイズがかわいい」、「このレーベルの装丁渋い!」、「特大帯(全体を覆うほぼカバーのような帯)付いてるとイメージ変わっておもしれ~」と、見た目も楽しむようになってきました(笑)
もっと知りたい「新書」の世界
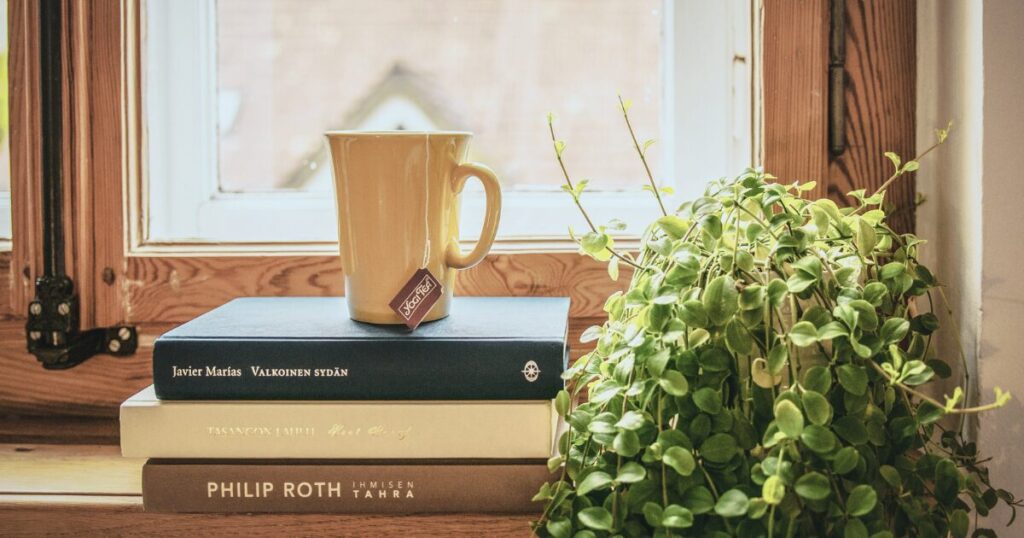
そんなわけで、最近ハマりつつある「新書」の世界について、「にわか本好き」(何回言うんだ)なりに語ってみました。
もともと知的好奇心がつよく、「知らない世界を知ること」に楽しさを覚える性格でした。
そのための手段のひとつが読書だったわけですが、今まであまり意識していなかった(というか、若干避けてた?)新書というものに興味を持ったことで、読む本の選択肢が一気に広がった気がします。
とはいえまだまだ新書ビギナー。
これからもっといろんな本を読んで、ときに当たって砕けながら(笑)、自分にとって面白い本と出会える率を高めていけたらいいなと思っています。
以前の私のように、今まで新書を選択肢に入れてこなかった方が、「今度新書コーナーに行ってみようかな?」と思ってくれたら嬉しいです!
お前はどの立場なんだって感じですが(笑)
それでは、あでぃおす!ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ